高校で留年するとどうなる?基準・判定の流れ・その後の選択肢を徹底解説
「高校で留年したらどうなるの?」——この問いは、多くの保護者が一度は抱く不安ではないでしょうか。出席不足、成績不振、提出物の未完など、理由はさまざまですが、留年は“いきなり”決まるものではありません。
本記事では、元高校教師の筆者が、留年の判断基準・通知のタイミング・その後の選択肢をわかりやすく解説します。さらに、「家庭でできる予防とサポート」の具体例も紹介。お子さんが“つまずき”を乗り越え、再び自信を取り戻すための道筋を一緒に考えていきましょう。
高校で留年するとどうなる?—基準(出席日数・成績・単位)と「いつ分かるか」を先に把握
高校で留年するとどうなる?
高校の留年は3つの基準——出席日数・成績・単位のいずれかが不足すると発生。
出席日数:授業の3分の2以上が必要。欠席超過は単位認定外になることも。
成績:赤点(60点未満)や提出物の未提出が続くと補習・追試対象に。
単位:1教科でも単位未修得があると進級不可(再履修や留年に)。
進級判定の時期:多くは2〜3月の学年末会議。補習・追試を経て最終判断。
早期の兆候:面談・成績表・呼び出しなど「警告段階」での対応が重要。
家庭でできる対策:欠席・提出物の可視化と早めの学校相談でリスク軽減。
出席日数の目安は「授業の3分の2以上」:欠席超過は追試の対象外になることも(出席不足は厳格)

「うちの子、このまま休みが続いたら留年になってしまうのでは…?」――高校生活を送るお子さんを持つ保護者なら、一度はそんな不安を感じたことがあるかもしれません。
実は、高校では“出席日数”がきわめて重要で、授業の3分の2以上の出席が単位取得の条件とされています。
この「3分の2」という基準は、全国の多くの高校で共通しています。たとえば90時間の授業がある科目なら、60時間(=3分の2)を下回ると、その科目の単位を認定してもらえません。
つまり、どんなにテストで点数を取っても、出席が足りないと自動的に“単位未修得”=留年リスクが発生してしまうのです。
しかも、出席不足の生徒は「追試」「補習」の対象から外れるケースが多く、成績で挽回するチャンスすらなくなることがあります。学校側も公平性を保つために、欠席が多い生徒に特別な救済措置を取るのは難しいのが現実です。
もちろん、病気・けが・家族の事情などやむを得ない理由がある場合は、医師の診断書や学校への事前相談によって、出席扱い・公欠として認められることもあります。
しかし、それも「申請しておけば自動的にOK」というわけではなく、担任・教務・保健室の連携が必要です。早めに相談しておくことが、後悔を防ぐ何よりのカギになります。
高校での「出席不足=留年」のルールは冷たく感じるかもしれませんが、実際には、毎日の積み重ねが評価されるシステムとも言えます。
遅刻・早退も積み重なると欠席換算されることがあるため、日々の登校リズムを整えることが最も確実な予防策です。
もし「最近、朝起きられない」「行く気力が落ちている」と感じたら、
単なる怠けではなく、メンタル面のサインかもしれません。
まずは欠席理由を責めるよりも、体調や気持ちを見つめ直す時間を持つことが大切です。
出席状況が厳しくても、学校側は“戻る意志”がある生徒には全力でサポートしてくれます。
高校の出席日数は、単なる数字ではなく「今、何を優先すべきか」を見直すバロメーターです。焦らず、でも早めに動くことで、留年を防ぐチャンスは必ず残されています。
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出席日数の基準 | 各教科で授業の3分の2以上の出席が必要。これを下回ると単位認定されない。 |
| 欠席が多い場合 | どんなにテストで点を取っても、出席不足は自動的に単位未修得扱いとなる。 |
| 追試・補習の扱い | 欠席が多い生徒は追試・補習の対象外になることがある。救済措置を受けにくい。 |
| 遅刻・早退の換算 | 3回の遅刻や早退で1欠席とみなされるなど、学校ごとの内部規定がある。 |
| 病気・通院などの事情 | 医師の診断書・保護者申請などにより、公欠・出席扱いになる場合も。早めの相談が重要。 |
| 留年リスクを下げるには | 出席管理を家庭でも共有し、欠席カレンダー・担任相談を早期に実施する。 |

成績不振と赤点・提出物・授業態度:学年末までの挽回と追認試験・補習・レポート提出の仕組み
「テストの点が悪かったら、もう留年になってしまうの?」——高校生の保護者にとって、もっとも気になるのがこの部分ではないでしょうか。
実際、高校の進級や単位認定は「テストの点数だけ」で決まるわけではなく、提出物・授業態度・補習への取り組みも大きく関わっています。
まず基本として、高校では各科目に「評価基準」があり、定期テストの点数が一定のライン(多くは60点未満=赤点)を下回ると、成績不振として扱われます。
ただし、赤点だから即留年というわけではありません。学校側は、学年末までに挽回できるように、補習・追認試験・レポート提出といった救済措置を用意していることが多いのです。
たとえば「赤点が2科目以上」や「提出物未提出が複数ある」場合には、放課後や長期休業中に補習が組まれます。その内容は、授業の再確認やプリント提出、ミニテストなどさまざま。
追認試験では、再テストで基準点(多くは60点)を超えれば単位が認定されるケースもあります。
ただし、ここで重要なのは「提出物と態度」です。補習や追認試験の対象になるかどうかは、日ごろの授業への姿勢や提出状況で判断されることが多く、“やる気を見せているか”が実は大きなカギになります。
教師も人間です。真剣に取り組んでいる生徒には、最後までチャンスを残そうとするものです。
一方で、「補習に来ない」「レポートを出さない」「遅刻・欠席が多い」などの状態が続くと、学年末の追認対象から外れてしまうこともあります。
この場合、成績が確定し、単位を落とす=留年の可能性が一気に高まります。つまり、留年を防ぐ一番の方法は、“最終的に帳尻を合わせる”努力を続けることなのです。
「今からでも間に合う?」という問いに対しては、答えはYesです。学年末までは時間があります。お子さんが焦りすぎないように、「何が足りないのか」を一緒に確認して、提出物→小テスト→補習と段階的に立て直していきましょう。学校側は、意欲がある生徒を決して見捨てません。
高校での成績不振や赤点は、ゴールではなく立て直しのチャンスです。家庭でできることは、「叱る」よりも「支える」。一歩ずつ課題をクリアしていけば、留年の不安は現実ではなくなります。
進級判定のタイミング:学年末(学年末評価→補習→追試→追認)の流れと学校ごとの差
「うちの子、このままで進級できるのかな?」——高校生活も終盤に差しかかると、多くの保護者が気にかけるのがこの点です。高校では、留年か進級かを最終的に判断する進級判定会議があり、そのタイミングは多くの場合、2月〜3月の学年末に行われます。
進級判定は、学期末の成績だけでなく、1年間の総合評価をもとに決定されます。一般的な流れは、次のようなステップです。
- ① 学年末評価:各教科担当が出席状況・定期テスト・提出物・授業態度を総合的に評価。
- ② 補習期間:成績不振の生徒に対して、追試や課題提出で挽回のチャンスを設定。
- ③ 追試・追認試験:補習の結果をもとに、基準を満たした生徒は単位認定。
- ④ 進級判定会議:教務・学年主任・担任らが集まり、最終的な進級可否を決定。
この流れを見るとわかるように、「留年が決まる」のは一瞬ではなく、段階的に判断されているのです。つまり、学年末評価の段階で“危険信号”が出ても、補習や追試で挽回できるチャンスが残されています。
多くの学校では「本人の努力」と「学習意欲」を重視しており、最後まであきらめなければ道は閉ざされません。
ただし、学校によってこの判定スケジュールには差があります。私立高校では比較的早め(2月中旬ごろ)に判定が行われ、補習も短期間で集中実施されるケースが多いです。
一方、公立高校では3月上旬に補習・追認試験が行われ、最終会議で進級・留年が確定します。
また、最近では「単位制高校」「総合選択制」を採用する学校も増えており、科目ごとに単位を積み上げるスタイルになっています。
この場合は、“留年”というよりも「不足単位を翌年度に再履修する」形となり、全体の進級は認められることもあります。高校によって仕組みが違うため、学年末前に担任や教務に確認することが何より大切です。
「まだ挽回のチャンスはあるのか」「いつまでに何をすれば間に合うのか」——そう感じたときこそ、行動を起こすタイミングです。
早めの相談と具体的な対策が、留年を防ぐ最大の鍵になります。焦らず、そして諦めずに、子どもの努力を支える環境を整えていきましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 進級判定の時期 | 多くの高校では2〜3月の学年末に実施。成績と出席の最終確認が行われる。 |
| 評価の流れ | 学年末評価 → 補習 → 追試 → 追認試験 → 進級判定会議という段階的なプロセス。 |
| 学年末評価 | 1年間の総合成績をもとに、出席・提出物・授業態度を含めて判断。 |
| 補習・追試 | 成績不振の生徒に再評価のチャンス。努力や提出物の改善で単位取得が可能。 |
| 学校ごとの差 | 私立は早め(2月中旬)、公立は3月上旬に実施。単位制では科目ごと判定の場合も。 |
| 留年回避のポイント | 早期の相談と補習参加。担任・教務と連携して改善計画を立てることが重要。 |
留年が告げられる前の“警告”と相談ルート:学年団・担任・教務・保健室登校などの救済例
「突然“留年です”と告げられることはあるの?」——高校に通うお子さんを持つ保護者の方なら、誰もが気になるところです。実際には、留年はある日突然決まるものではなく、必ず“前触れ”があります。
そのサインを早めにキャッチし、学校とつながって動くことができれば、進級のチャンスを取り戻せることも少なくありません。
まず、学校での“警告サイン”として多いのは、定期テスト後の呼び出し・成績表への注意マーク・三者面談での指摘などです。特に学年末が近づくと、「このままだと単位が危うい」といった具体的な表現で伝えられることがあります。
これは、学校側が“今ならまだ間に合う”というメッセージを出している段階。ここで行動できるかどうかが、留年を防ぐ分岐点になります。
この段階で頼りになるのが、まず担任の先生です。出席・提出物・成績など全体を見ているため、「どの科目が危険なのか」「補習やレポートで挽回できるか」を具体的に教えてくれます。
さらに、学年団(学年主任や担当教員グループ)は、学校全体の方針や救済措置を決定する立場にあり、場合によっては柔軟な対応をしてくれることもあります。
保健室の先生は、生徒と教員の間をやわらかくつなぐ存在。担任より相談しやすいと感じる子も多いので、保護者から連携をお願いしてみるのも効果的です。
さらに、出席や成績に関わる最終判断を担うのが教務主任です。教務は「制度の窓口」として、出席日数の扱いや補習・追試の規定を正確に把握しています。
もし「病気で休んだ日をどう扱うのか」「追認試験の対象になるか」など制度的な部分に疑問があるときは、教務への相談が確実です。
重要なのは、“本人だけに任せない”という姿勢です。高校生は思春期の真っ只中で、「もうダメかも」と感じたときほど、自分から動けなくなります。
そんな時、保護者が一緒に学校へ相談に行くことで、先生側も「家庭もサポートしてくれている」と前向きに受け止め、対応を考えてくれることが多いのです。
高校で留年がどうなるかは、決して一方的な“結果”ではなく、関係者が動いた分だけ変えられるプロセスです。警告を受けた時点で「もう終わり」ではありません。むしろ「まだ間に合う」という合図。早めの対話と小さな行動が、進級への道を再び開く第一歩になります。
留年が決まった/濃厚になった後の選択肢—「原級留置」だけではない
留年が決まった/濃厚になった後の選択肢
原級留置(再履修):同じ高校で在籍を続け、不足単位のみを取り直す方法。担任変更・時間割再編あり。
通信制高校への転入/編入:留年の概念がなく、落とした科目だけ翌年再履修できる。柔軟な学習ペース。
単位制高校への転入:科目ごとに単位を積み上げるスタイル。進級・留年の区別があいまいで学び直しやすい。
定時制高校への転入:昼・夕・夜間など通学時間を選べる。働きながらでも卒業可能。学費も比較的安い。
高卒認定試験(旧大検):高校を辞めても、高卒と同等の資格を取得できる。大学・専門学校進学も可能。
再登校支援・相談窓口の利用:教育委員会・スクールカウンセラー・NPOなどの相談ルートを早めに確保。
家庭での支え方:焦らせず、「どうしたいか」を一緒に整理。次の一歩を本人主導で決めることが再スタートの鍵。
同じ高校での再履修:不足単位の取り直しとメンタル面の注意点(クラス変更・時間割再編)

「留年した場合、同じ高校に通い続けることはできるの?」——そう感じる保護者の方は多いと思います。結論から言うと、高校で留年が決まっても、ほとんどの場合は同じ学校で再履修(=もう1年やり直し)することが可能です。
特に公立高校では、原級留置と呼ばれる制度により、同じ学校・同じ課程に在籍したまま、落とした単位を取り直すことができます。
再履修とはいっても、単に「同じ授業を最初から受ける」というより、不足した科目だけを中心に学び直すケースが一般的です。
そのため、すべての授業に出席するわけではなく、履修していない時間帯は自習や補習に充てられることもあります。学校によっては、時間割を再編して「午前は再履修、午後は補習」など、無理のないスケジュールを組んでくれることもあります。
ただし、再履修には大きな変化も伴います。たとえば、クラスが変わるケースがほとんどです。仲の良かった友人が進級してしまい、1年下の学年に入ることになると、孤立感や疎外感を感じやすくなります。
このときに必要なのは、「自分を責めすぎない」ことと「新しい環境にゆっくり慣れていくこと」です。
実際、再履修の1年は、本人にとって精神的な再スタートの年でもあります。留年という事実にショックを受けるのは当然ですが、その分だけ「もう一度立て直す」ための時間が与えられたとも言えます。
高校によっては、カウンセラーや保健室の先生が定期的に面談をしてくれたり、再履修生専用のサポート体制を設けている場合もあります。
保護者としては、「どうしてこうなったの?」と問い詰めるよりも、「これからどうしたいか」を一緒に考える姿勢が大切です。本人が「もう一度頑張りたい」と思える環境づくりをサポートすることで、再履修の1年が“取り戻しの1年”に変わっていきます。
高校で留年するとどうなるのか――同じ学校での再履修は決して後退ではありません。むしろ、じっくり自分を見つめ直し、「学び直しの力」を育てる貴重な時間です。焦らず、周囲とつながりながら、新しい一歩を踏み出せば、次の進級もきっと見えてきます。
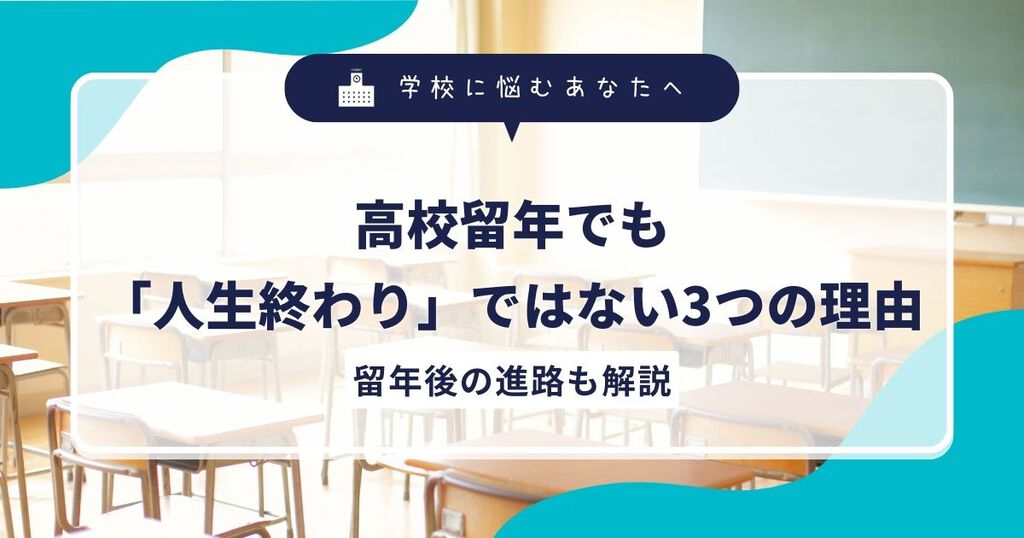
通信制・単位制への転入/編入:留年の概念が薄く、落とした科目のみ翌年再履修できる利点
「高校で留年したらどうなるの?」「他の学校に移るしかないの?」
——そんな不安を抱いたとき、選択肢のひとつになるのが通信制高校や単位制高校への転入・編入です。これらの学校では、一般的な全日制とは異なり、“留年”という概念がほとんどありません。
通信制・単位制高校の最大の特徴は、単位を積み上げて卒業を目指す仕組みにあります。つまり、全科目を一度に修得しなくても、落とした科目だけを翌年再履修すればOK。やり直しのハードルが低く、無理なく自分のペースで進めることができます。
たとえば、全日制高校では3年分の学年ごとに進級判定が行われ、「どれか1教科でも単位を落とすと進級できない」こともあります。
しかし通信制や単位制では、1年で取れなかった科目があってもそのまま翌年度に持ち越して再履修できるため、「留年」ではなく「ペースを調整して学び続ける」という考え方が基本です。
また、通信制高校では、自宅学習+スクーリング(登校日)+レポート提出で単位を取る形式が一般的。通学日数は少なく、働きながら学ぶ人や、体調面に不安がある生徒にも向いています。
単位制高校では、全日制に近い通学スタイルを保ちながらも、履修科目を自由に選べる柔軟さがあります。
こうした仕組みは、一度つまずいた生徒にとって“リスタートのしやすい環境”になります。高校で留年が決まりそうな状況でも、通信制や単位制に転入することで、これまでに取った単位を引き継ぎながら再スタートできるのです。
転入時には在籍高校からの「成績証明書」が必要ですが、単位の認定が通れば時間も学費も大幅に節約できます。
一方で、通信制や単位制では“自分で管理する力”が求められます。レポートの締切やスクーリング日を自分で把握し、計画的に進めなければなりません。自由=自己管理がカギになるため、保護者のサポートや声かけが大きな助けになります。
高校で留年するとどうなるかを考えたとき、「通信制や単位制に移る」というのは逃げではなく、もう一度“自分に合った学び方”を選び直すチャンスです。
無理に全日制のペースに合わせるよりも、心と体に合った形で学びを続けることが、結果的に卒業への一番の近道になるのです。
定時制高校という選択:学費・就労両立・通学時間帯の柔軟性(転入/編入の注意点)
「高校で留年したらどうなるのか」
「もう一度やり直すならどんな道があるのか」
——そう考えたとき、現実的で前向きな選択肢のひとつが定時制高校です。
定時制は“夜の高校”というイメージを持たれがちですが、今では昼間・夕方・夜など、多様な通学スタイルを選べる柔軟な仕組みに変わっています。
定時制高校の特徴は、まず授業が4年制である点です。1日に受ける授業数が少なく、1年ごとの負担が軽いため、働きながら・体調を整えながらゆっくり卒業を目指せます。
実際に、昼はアルバイトや仕事をし、夜に登校する生徒も少なくありません。最近では「午前部」「午後部」「夜間部」など、ライフスタイルに合わせて選べる学校も増えています。
また、学費の面でも定時制は安心です。授業料は全日制よりも低く、就学支援金制度を活用すれば自己負担をほぼゼロにできる場合もあります。
経済的な事情で一度高校を離れた生徒にとって、再スタートを切りやすい環境が整っています。
学びの内容は全日制とほぼ同じで、卒業すれば「高卒資格」は同等です。
違いは“進むスピード”だけ。出席や課題の提出をしっかり積み重ねれば、大学や専門学校への進学も十分可能です。
高校で留年した後どうなるかという不安を抱く生徒にとって、
定時制は「もう一度自分のペースで学びたい」という希望を叶える場とも言えます。
ただし、転入・編入を検討する際には注意点もあります。
まず、在籍高校の成績証明書と単位認定が必要になります。
これまでに取得した単位がどの程度引き継げるかは学校ごとに異なるため、
希望する定時制高校に直接確認することが大切です。
また、転入(在籍期間が継続)と編入(いったん退学して入り直す)では
手続きの流れが異なるため、タイミングを誤らないようにしましょう。
さらに、定時制は自由度が高い分、自己管理が求められる環境でもあります。
登校時間が遅い分、生活リズムが崩れやすかったり、モチベーションを保つのが難しいと感じる生徒もいます。
保護者としては、出席や提出物を見守りながら、小さな成功体験を積ませるサポートが大切です。
高校で留年してしまっても、「もう終わり」ではありません。定時制高校という道は、焦らず、自分のリズムで学び直すチャンスです。夜風の中で登下校する姿には、周りには見えない努力と決意が詰まっています。環境を変えることで、お子さんの未来が再び動き出すことも多いのです。
転入と編入の違いを整理:在籍の連続性・単位の引継ぎ・手続きで見落としやすい点
「高校を移るとき、転入と編入の違いって何?」——この質問は、留年や進路変更を考えるご家庭でよく出る疑問です。実はこの2つ、似ているようで法的な扱いと手続きのタイミングが大きく異なります。違いを知っておくことで、後悔のない選択ができるようになります。
まず、転入(てんにゅう)とは、今在籍している高校を辞めずに、在籍のまま別の高校へ移ることです。つまり、在籍の連続性が保たれるのがポイントです。
転校と同じイメージで、在籍証明書や成績証明書をもとに、新しい高校が単位を引き継ぎ、学年を継続してくれる場合が多いです。
一般的には、学期の途中や学年末前に行われることが多く、手続きがスムーズに進めば留年せずに次の学校で学びを続けることが可能です。
一方、編入(へんにゅう)は、いったん前の高校を退学してから、改めて別の高校に入り直すことを指します。この場合、在籍の連続性は途切れるため、単位の引き継ぎが認められないこともあります。
特に、退学から期間が空くと、取得済み単位が無効になってしまうケースもあるため注意が必要です。
たとえば、前の高校で1年次の単位をすべて修得していれば、編入先で「2年次」として受け入れられる可能性がありますが、未修得科目があると「1年次からやり直し」と判断される場合も。
学校ごとに単位認定の基準が異なるため、転入・編入を検討する際は、まず受け入れ先の学校に確認することが重要です。
また、手続き上の落とし穴として見落とされやすいのが、「時期」と「書類」です。転入は受け入れ可能な時期が限られており、学期途中だと募集を締め切っている学校もあります。
必要書類は、在籍高校からの「在学証明書」「成績証明書」「単位修得証明書」など。編入の場合はこれに加え、退学証明書が必要になります。
さらに、転入・編入のどちらを選ぶ場合でも、受け入れ先の学校が単位をどこまで認めてくれるかが肝になります。学校によっては同じ科目名でもカリキュラムが違うため、すべての単位がそのまま移行できるわけではありません。
この点を見落とすと、「思ったより多くの単位を取り直す必要がある」という事態になりかねません。
高校で留年するとどうなるかを考えるとき、転入や編入は“リセット”ではなく、“引き継ぎのチャンス”です。焦って手続きを進めるのではなく、在籍校と転入先の双方に相談し、書類・時期・単位認定を丁寧に確認することが、スムーズな再スタートにつながります。
留年を防ぐ・乗り越える家庭の実践—“学びを止めない”仕組みづくり
留年を防ぐ・乗り越える家庭の実践
欠席・遅刻を“見える化”:カレンダーや表で出席状況を共有し、早めにリスクを把握。
医療・通院対応を記録:診断書や配慮申請を学校へ提出し、出席扱い・公欠の認定を確実に。
赤点予防のPDCA:提出物→小テスト→補習→追試→追認の流れを計画的に回す。
家庭学習の習慣化:短時間×高頻度で“提出物完了→復習→確認テスト”のループを定着。
先生との対話を前倒し:担任・教務・保健室など複数ルートで相談し、救済策を早期に確保。
メンタルケアも重視:責めるより“見守る”姿勢で、安心して立て直せる家庭環境を整える。
行動を複線化:再履修・転入・通信制など、複数の進路を比較しながら柔軟に選択。
欠席・遅刻の可視化と早期アラート:出席カレンダー/通院・配慮申請/教科ごとの出席率管理

「気づいたら欠席が多くなっていた」「あと何日休んだら単位が危ないのか分からない」——高校で留年するとどうなるかを考えるとき、最も重要なのは“早期の気づき”です。出席日数は単位認定のベースであり、授業の3分の2以上の出席が求められます。つまり、気づくのが遅れるほど、リカバリーが難しくなります。
そこでおすすめなのが、家庭でも簡単にできる「出席カレンダー」の活用です。日ごとの出欠をカレンダーに記録し、欠席・遅刻・早退を色分けするだけで、視覚的に状況が把握できます。
赤(欠席)、黄(遅刻・早退)、青(登校)など、見える化することで「もう少しで危険ライン」というタイミングをすぐに察知できます。
さらに、体調不良や通院などやむを得ない事情がある場合は、医師の診断書や通院証明をもとに学校へ「配慮申請」をしておくことが重要です。
学校によっては、保健室登校や別室登校の記録を“出席扱い”にしてくれるケースもあります。早めに担任や保健室の先生に相談することで、欠席日数が「無断欠席」としてカウントされるリスクを減らせます。
また、全体の出席日数だけでなく、教科ごとの出席率を意識することも大切です。高校の単位は科目単位で認定されるため、特定の教科だけ欠席が多いと、その教科の単位を落とす可能性があります。
家庭で週に一度、時間割に沿って「出席状況チェック表」を作成し、苦手な科目ほど丁寧に確認しておくと安心です。
最近では、スマートフォンのカレンダーアプリやスプレッドシートを使って、自動的に出席率を計算できるようにしている家庭もあります。ICTを活用して可視化すれば、お子さん自身も「あと何回休めるか」を数字で把握できるため、自己管理の意識が自然と高まります。
高校で留年したらどうなるかを心配するよりも、その前に「どこで立ち止まっているのか」を見える形にすることが大切です。欠席や遅刻の見える化は、叱責ではなく支援のためのツール。
数字で把握できれば、「もう少し頑張ろう」と本人が思えるきっかけにもなります。早めの気づきと対話が、留年を防ぐ第一歩です。
“赤点予防”の学期内PDCA:提出物・小テスト・再評価(補習→追試→追認)へ向けた逆算計画
「テストの点が悪くても、まだ間に合うの?」——高校で留年するとどうなるかを気にする保護者にとって、気がかりなのは「どこで挽回できるか」ではないでしょうか。
実は、赤点を取る前に防ぐための仕組みを家庭でもつくることができます。それが、学期内の“PDCAサイクル”を回すことです。
PDCAとは、Plan(計画)→Do(実行)→Check(確認)→Action(改善)のサイクル。
企業の経営だけでなく、学校生活にも応用できます。
高校の場合、このサイクルを「提出物・小テスト・補習」に当てはめることで、“赤点予防”を早めに仕掛けることができるのです。
まずPlan(計画)。テスト範囲表が配布されたら、まず「何を、いつまでに提出するか」を一緒に書き出しましょう。特にワークやノート提出は、提出率=成績評価に直結します。学校によっては、提出物未完で自動的に評価が下がることもあります。
次にDo(実行)。計画に沿って学習を進めます。提出物を単なる“提出するための作業”にせず、小テストや授業内容を絡めながら復習ツールに変えることがポイントです。赤線を引く、要点をまとめるなど、理解を「見える形」にしておくと後からのチェックがしやすくなります。
Check(確認)では、小テストや小課題の結果を必ずふり返ります。「間違いが多い=理解が浅い」サイン。ここで立ち止まれば、本テストでの赤点を未然に防げます。先生から返却されたプリントを“そのままにしない”ことが重要です。
そして最後のAction(改善)。もし結果が思わしくなければ、補習や追試、追認などの機会を活かします。多くの高校では、一定の条件を満たせば追試で再評価される制度があります。
「赤点=即留年」ではありません。努力の継続を示すことで、先生の評価や救済の対象に入る可能性が高まります。
学期の後半になるほど「もうダメかも」と感じやすい時期ですが、実際はここからの巻き返しが可能です。たとえ小さな提出物でも、ひとつずつ積み重ねれば評価は確実に変わります。
高校の先生たちは、“最後までやり切る姿勢”を必ず見ています。
高校で留年したらどうなるかを考える前に、「今からできる改善」に目を向けることが大切です。提出物・小テスト・補習をひとつの流れとして管理すれば、赤点の“予防線”を早めに引けます。焦らず、丁寧に、そしてコツコツと。学期の終盤こそ、努力が“評価”に変わるタイミングです。
家庭学習の重要性:短時間×高頻度で単位取得に直結する“提出物完了→復習→確認テスト”ループを習慣化(学年末の救済を活かす土台づくり)
「学校では補習や追試もあるのに、家庭学習って本当に必要?」——そんな疑問を持つ方も多いでしょう。けれど、高校で留年するとどうなるかを考えるとき、いちばん大切なのは日々の積み重ねです。
特に、高校の評価は“テストの点”だけでなく、提出物や小テスト、授業態度が単位認定に直結します。つまり、家庭学習は“救済を受けられる力”を育てるための土台なのです。
家庭学習というと「長時間やらなきゃ」と思われがちですが、実際には短時間×高頻度が効果的。1日30分でも構いません。授業があったその日のうちにノートを見返し、出された課題を少しずつ進める。
この“即復習”のリズムが、理解の定着と提出物完了の両方を支えます。提出物をためこまずに進めることができれば、学期末に慌てることもなくなります。
家庭学習の理想的なサイクルは、「提出物完了 → 復習 → 確認テスト」のループです。提出物を仕上げながら復習を行い、テスト前には自分の理解度を“ミニテスト”でチェック。
これを繰り返すことで、学期ごとの成績が安定し、赤点や補習の対象になるリスクを下げられます。結果として、留年を防ぐ「見えない保険」をかけることになるのです。
また、家庭学習には「努力の記録」という意味もあります。提出物が整っている、生徒自身がノートを工夫している――そうした姿勢は、教師にしっかり伝わります。高校の先生たちは、“日々の努力が見える生徒”にこそ救済措置を与えたいと考えています。つまり、家庭での小さな習慣が、学年末の追試や追認のチャンスを広げるのです。
忙しい保護者の方でも、サポートは難しくありません。たとえば、「今日は何の授業があったの?」「提出物はどこまで進んだ?」と一言聞くだけで十分です。干渉ではなく“見守り”の姿勢が、子どものやる気を引き出します。短い声かけでも、安心感が家庭学習の継続力につながります。
高校で留年したらどうなるかを考えると気が重くなりがちですが、日々の家庭学習はその不安を小さくする最良の方法です。机に向かう時間を“義務”ではなく、“自分の未来を守る習慣”と捉えられれば、どんな子でも少しずつ前に進めます。家庭での10分が、進級のための確かな一歩になるのです。
高校で留年するとどうなる?まとめ—基準を早く把握し、救済策と進路の“複線化”でリスクを下げる(相談は前倒しで)
高校で留年するとどうなるのか——。その答えは、出席日数・成績・単位の3つの基準がどの段階で崩れるかによって大きく変わります。しかし、共通して言えるのは、早めに気づき、早めに動くほど、救済の道が広がるということです。
出席不足は「授業の3分の2未満」で即単位未修得となる可能性があり、補習や追試も対象外になります。成績不振でも、授業態度や提出物の積み重ねが評価されれば、追認・補習・再テストのチャンスをもらえるケースが少なくありません。
学校は“最後まで諦めない生徒”を応援する体制を持っています。
それでも進級が難しい場合は、同じ高校での再履修・通信制や単位制への転入・定時制高校への編入など、複数の選択肢が用意されています。これらはいずれも「留年=失敗」ではなく、「もう一度学びを取り戻す仕組み」。制度を知ることが、未来を開く第一歩です。
また、家庭でのサポートも重要な鍵となります。欠席の可視化や提出物の管理、短時間の復習習慣づくりなど、小さな行動が積み重なることで、留年リスクを大きく下げられます。
お子さんにとって家庭は「責められる場所」ではなく、「安心して立て直せる場所」であることが、何よりの支えになります。
そして何より大切なのは、相談を前倒しにすることです。担任や教務、スクールカウンセラー、保健室など、どのルートからでも構いません。「気になる」と思った時点で動くことで、進級・再履修・転入の選択肢が広がります。
高校で留年がどうなるかは、運ではなく“行動のタイミング”で変わります。
焦らず、あきらめず、複線的に考える。早めの一歩が、未来を守る最良の方法です。今できることを、ひとつずつ進めていきましょう。

