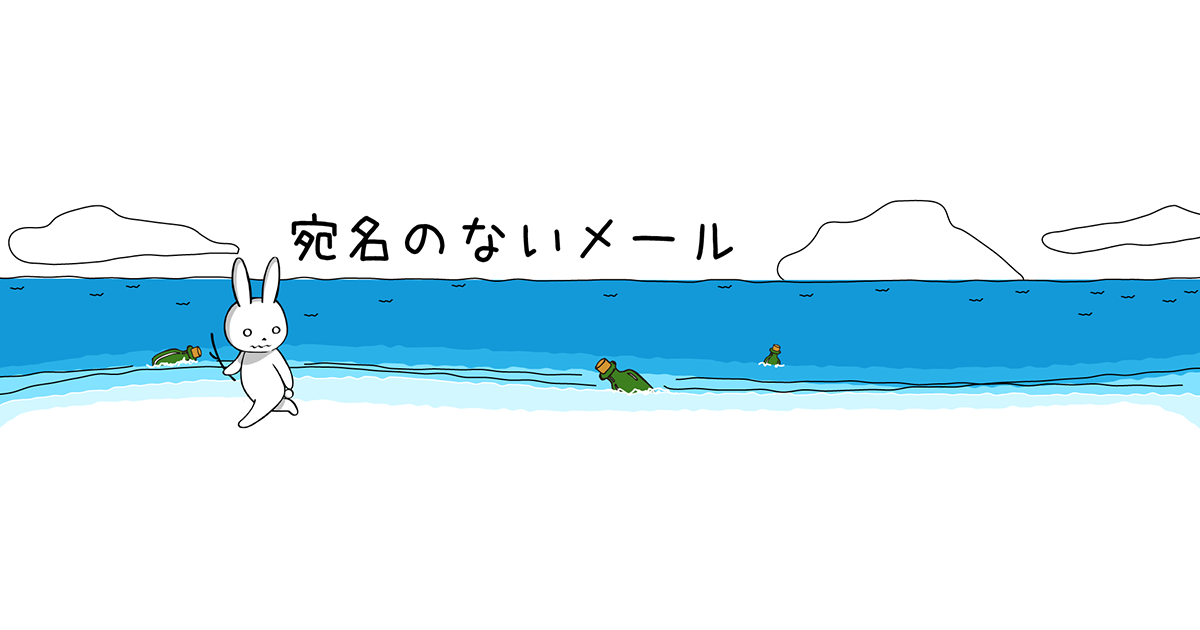高校で「友達はいるけど楽しくない」と言う我が子に、親ができること
高校に通うわが子が「友達はいるんだけど、なんか楽しくない」とつぶやくと、
親として胸がぎゅっと痛みますよね。
いじめではない、休むほどつらいわけでもない。
でも毎日の学校生活がどこか重い——そんなグレーな悩みを抱える高校生は少なくありません。
実はこの状態には、思春期特有の心理や環境の変化が大きく影響しています。
この記事では、元教師の視点から「原因」と「親ができるサポート」を整理し、最終的に子どもの自立につながる関わり方をわかりやすくお伝えします。
高校で「友達はいるけど楽しくない」と感じるのはおかしくない?親がまず知っておきたいこと
「いじめられているわけじゃないのにしんどい」——よくある高校生活のモヤモヤパターン

「いじめられているわけじゃないのにしんどい」と子どもがつぶやくと、
親としてどう受け止めればいいのか迷いますよね。
実は、「高校 友達いるけど 楽しくない」という状況は、いまの高校生にとてもよくある悩みです。
表面上は笑って友達と過ごしていても、内側では「無理をしながら合わせているだけ」
というケースは少なくありません。
なぜ、いじめがないのにしんどさが出てしまうのでしょうか。
多くは、高校特有の人間関係の変化が影響しています。
クラス替えで環境が大きく変わり、仲の良い友達とクラスが離れる。
新しいグループに入ろうとしても、すでに雰囲気ができていて入りづらい。
そんな中で、「とりあえず一緒にいる友達」はできても、“本音で話せる友達”とは限らないんですよね。
あなたの子どもも、もしかすると“愛想笑いでその場に合わせ続けている”のかもしれません。
見た目は普通に学校生活を送っているように見えても、内側では疲労がたまっていく。
本人も「理由はよくわからないけどしんどい」と感じてしまう。
そう考えると、決して特別な悩みではないことがわかります。
では、親としてどう関われば良いのでしょうか。
まず大切なのは、子どもが感じているモヤモヤを否定せずに、そのまま受け止める姿勢です。
「そんなふうに感じてたんだね」「しんどいって思う理由、もっと聞かせてほしいな」
と声をかけるだけで、子どもは安心して気持ちを整理しはじめます。
そのうえで、今の状況は「いじめではないけれど、誰もが経験しやすい揺らぎ」であることを伝えると、
子どもは「自分だけじゃないんだ」とホッとします。
親が慌てて原因探しをしなくても大丈夫です。
まずは、子どもの言葉をていねいに拾うこと。
それが、これからの高校生活を立て直すための大事な一歩になります。
こうして段階を踏んでいくことで、あなた自身も気持ちがスッと軽くなり、
「次にどう動けばいいか」が見えやすくなっていきます。
中学とのギャップと「理想の高校生活」とのズレが、高校が楽しくない理由になる
中学とのギャップと「理想の高校生活」とのズレが、
高校が楽しくない理由になることは珍しくありません。
実際、「高校 友達いるけど 楽しくない」と感じる子の多くが、
この“ギャップ疲れ”に悩んでいます。
あなたのお子さんも、どこかで「中学のほうが気楽だったな…」と感じていないでしょうか。
中学では、同じ地域・同じ価値観で育った仲間が多く、暗黙のルールや距離感も似ていました。
それが高校に入ると一気にバラバラになります。
学力、家庭環境、趣味、考え方…これまで当たり前だった「空気」が通じない。
だからこそ、新しい友達ができても、
“友達はいるのに楽しくない”という不思議な状態になりやすいのです。
さらに、多くの子は「高校に入ったら楽しくなるはず」という理想を持っています。
青春、部活、恋愛、キラキラした日々…。
SNSの影響もあって“楽しさのハードル”が上がりがちです。
しかし現実は、勉強の難しさや人間関係の複雑さ、生活リズムの変化など、
地味なストレスがじわじわ積み重なります。
そのギャップに気づいたとき、「あれ?思ってたのと違う…」という失望感が生まれるんですね。
では親はどう支えればいいのでしょうか。
まず大切なのは、この“ギャップ疲れ”を普通の反応として扱うことです。
「そんなふうに感じる子、実はすごく多いよ」
「理想と違っても、それは悪いことじゃないよ」と、
子どもの気持ちに寄り添う形で伝えてあげてください。
否定されないことで、子どもは安心して次の一歩を考えられるようになります。
そして、焦って「友達は?部活は?もっと楽しんだら?」と急かさないこと。
高校生活は長いようで短いですが、心のペースは人それぞれです。
あなたの落ち着いた姿勢が、子どもにとって大きな支えになります。
こうした理解が積み重なると、子どもだけでなく、あなた自身も
「次にどう動けばいいか」が自然と見えるようになっていきます。
友達はいる=居場所がある、とは限らない——表面的な付き合いと自己肯定感の低下

友達がいるからといって、必ずしも「安心できる居場所がある」とは限りません。
実は、「高校 友達いるけど 楽しくない」という悩みの背景には、“表面的なつながりだけが残る”という状態がよくあります。あなたのお子さんも、笑顔で過ごしてはいるけれど、心の中では「本音を言える相手がいない」と感じているのかもしれません。
高校に入ると、クラスの雰囲気や価値観が一気に多様になります。
誰かに合わせて笑っておけばとりあえず輪に入れるし、いじめられるわけでもない。
だからこそ、「一緒にいる友達はいる」ように見えるのです。
でも、そこで交わされる会話が浅かったり、
自分の興味や考えを無理に抑えてしまったりすると、心の奥に疲れがたまっていきます。
特に真面目で優しいタイプの子ほど、「嫌われたくない」「空気を壊したくない」と感じやすく、
本音を後回しにしがちです。結果として、“友達はいるのに孤独”という矛盾した状態になります。
親から見ると「普通に友達いるじゃない」と思えるけれど、
本人の感覚はまったく別のところにあるのです。
では、そんなとき親はどう関わればいいのでしょうか。
まず大事なのは、「友達の数=居場所の深さではないよ」とさりげなく伝えてあげることです。
さらに、「無理やり合わせなくてもいいんだよ」「家はそのままのあなたでいていい場所だよ」と、
子どもが肩の力を抜ける環境をつくることが何よりの支えになります。
もう一つ大切なのは、子どもが“自分の好き”や“安心できる関係”を再確認できるように、
家庭で小さな会話の時間を作ることです。正解を押しつける必要はありません。
ただ、「その友達といるとどう感じる?」「どんな関係だと楽だと思う?」と、
ゆっくり問いかけていくだけで十分です。
こうした積み重ねが、子どもにとっての“本物の居場所づくり”につながり、あなた自身も「今できること」が自然に見えてくるようになります。
高校で「友達はいるけど楽しくない」子どもが抱えがちな原因と、環境を変えるヒント
「気の合う友達がいない」「グループに入りづらい」ときに、親がそっと聞き出したいポイント

「気の合う友達がいない」「グループに入りづらい」と感じる高校生は想像以上に多いものです。
だからこそ、子どもが「高校 友達いるけど 楽しくない」とこぼしたとき、
親がそっと“本音”を引き出すことが大切になります。表面的な言葉の裏には、
本人でも整理しきれていない小さな違和感が隠れていることが多いからです。
まず意識したいのは、「どうしたの?」ではなく、“どう感じているの?”という聞き方に変えることです。
「グループにいると疲れるの?」「どんな瞬間にしんどいって思う?」など、
感情に寄り添う問いが本音を引き出す鍵になります。
子どもは事実よりも“気持ち”を先に聞いてもらうことで、安心して心を開きやすくなります。
次に、少しずつ具体的に聞いていきましょう。「話が合わないのかな?」「価値観が違う感じ?」
と選択肢を示してあげると、子どもは自分の状態を言語化しやすくなります。
ここで親が焦ってアドバイスをしてしまうと心を閉ざしてしまうので、
“聞く:アドバイス=9:1”のバランスを意識するとよいでしょう。
そして忘れてほしくないのが、「気の合う友達は、無理して探すものではないよ」と伝えることです。
高校は人間関係の幅が広がる分、逆に「まだ出会っていない」だけの可能性もあります。
親がこの視点を示してあげるだけで、子どもは「あ、今の違和感は失敗じゃないんだ」
と気持ちが軽くなります。
最後に、子ども自身が“どんな関係なら安心できるか”
を考えられるように一歩だけ踏み込んで聞いてみましょう。
「どんな友達だと話しやすい?」「どんな距離感だと楽?」と問いかけることで、
自分に合う人間関係のヒントが見えてきます。
こうして丁寧に話を聞いていくと、子どもはもちろん、あなた自身も「今は焦る必要がないんだ」「次の展開が見えた」と少しずつ心がほどけていきます。
学校が楽しくないのは勉強だけが原因じゃない——プレッシャー・校則・先生との相性
「高校が楽しくない理由=勉強」と思われがちですが、実際にはそれだけではありません。
むしろ、「高校 友達いるけど 楽しくない」と感じる子の多くは、
勉強以外の“見えにくいストレス”に疲れてしまっています。
あなたのお子さんも、気づかないうちにいくつものプレッシャーを背負っているのかもしれません。
まず大きいのは、周囲との差を意識してしまうことです。
高校では学力が似た子が集まるため、「みんなできて当たり前」という空気が強くなりやすい。
テストの点や順位、提出物のスピード、部活との両立…。表では明るくしていても、
内心では常に比べてしまい、疲れがたまっていきます。
次に、校則やルールとの相性も見逃せません。「どうしてこのルールが必要なの?」
と納得できないまま従う日々は、意外と大きなストレスになります。
真面目な子ほど、「破りたくない・でも窮屈」と葛藤しやすく、
気持ちが押しつぶされそうになることもあります。
さらに、先生との相性も大きく影響します。授業の進め方が合わない、厳しすぎて話しづらい、
相談しても軽く流されてしまう…。
そうした積み重ねが、「学校=疲れる場所」という印象につながってしまうのです。
友達がいても楽しくないと感じるのは、こうした複合的なストレスが絡んでいるからこそです。
では、親としてできることは何でしょうか。
まずは、「勉強以外にもいろんな理由があるよね」と、子どもの“感じている疲れ”全体に共感を示すことです。
原因をひとつに絞らず、「どれが一番しんどい?」とゆっくり聞き出してあげると、
子どもは安心して話せるようになります。
そしてもうひとつ大切なのは、「今の環境がすべてじゃない」と伝えること。
クラス替え、先生の変化、部活の見直し、選択科目…高校生活には改善できる
ポイントが意外と多くあります。
こうして話を重ねていくうちに、子どももあなた自身も「解決の糸口はある」と感じられ、
次の展開が自然と見えてきます。
学校だけが世界じゃない——部活・アルバイト・オンラインなど「学校外の居場所」を一緒に探す

「高校が楽しくない理由=勉強」と思われがちですが、実際にはそれだけではありません。
むしろ、「高校 友達いるけど 楽しくない」と感じる子の多くは、
勉強以外の“見えにくいストレス”に疲れてしまっています。
あなたのお子さんも、気づかないうちにいくつものプレッシャーを背負っているのかもしれません。
まず大きいのは、周囲との差を意識してしまうことです。
高校では学力が似た子が集まるため、「みんなできて当たり前」という空気が強くなりやすい。
テストの点や順位、提出物のスピード、部活との両立…。
表では明るくしていても、内心では常に比べてしまい、疲れがたまっていきます。
次に、校則やルールとの相性も見逃せません。「どうしてこのルールが必要なの?」
と納得できないまま従う日々は、意外と大きなストレスになります。
真面目な子ほど、「破りたくない・でも窮屈」と葛藤しやすく、
気持ちが押しつぶされそうになることもあります。
さらに、先生との相性も大きく影響します。
授業の進め方が合わない、厳しすぎて話しづらい、相談しても軽く流されてしまう…。
そうした積み重ねが、「学校=疲れる場所」という印象につながってしまうのです。
友達がいても楽しくないと感じるのは、こうした複合的なストレスが絡んでいるからこそです。
では、親としてできることは何でしょうか。
まずは、「勉強以外にもいろんな理由があるよね」と、子どもの“感じている疲れ”全体に共感を示すことです。
原因をひとつに絞らず、「どれが一番しんどい?」とゆっくり聞き出してあげると、
子どもは安心して話せるようになります。
そしてもうひとつ大切なのは、「今の環境がすべてじゃない」と伝えること。
クラス替え、先生の変化、部活の見直し、選択科目…高校生活には
改善できるポイントが意外と多くあります。
こうして話を重ねていくうちに、子どももあなた自身も
「解決の糸口はある」と感じられ、次の展開が自然と見えてきます。
「高校は何のために行くの?」——進路や目的を言語化すると、高校生活の意味が少し見えてくる
高校生活がうまくいっていないと、どうしても「学校の中でなんとかしなきゃ」と思いがちです。
でも実は、「高校 友達いるけど 楽しくない」と感じている子ほど、
学校の外に小さな居場所をつくることで一気に気持ちが軽くなることがあります。
学校が世界のすべてに見えてしまう時期だからこそ、視野を広げるサポートが親にはできるのです。
まず候補になるのは、部活です。「もう部活入ってるけど…」という場合でも、
合わないなら無理に続ける必要はありません。別の部活に移ったり、文化部に変えたりするだけで、
まったく新しいつながりが生まれることがあります。
子どもには「高校では部活の出入りは珍しくないよ」と安心材料を渡してあげてください。
次におすすめなのがアルバイトです。学校の友達とは違う年齢・価値観の人たちと関わる経験は、
子どもにとって新鮮で刺激になります。「学校の自分」と「バイトの自分」が分かれることで、
心の余白が生まれます。保護者としては安全面や学校規定の確認が必要ですが、
合う子には大きな安心材料になります。
さらに、いまはオンライン上にも多様な居場所があります。
趣味のコミュニティ、創作グループ、音楽・ゲーム・学びの場…学校では出会えない
“同じ興味”の友達ができることは珍しくありません。
もちろん安全性の確認は欠かせませんが、今の高校生にとっては自然な社会参加のひとつです。
大事なのは、「学校でうまくいかない=すべて終わり」ではないことを
子どもに知らせてあげることです。
学校外にひとつ安心できる場所があるだけで、
心のバランスが整い、学校でのストレスも軽くなっていきます。
そして何より、子どもが新しい場所に踏み出す時、あなたの一言が大きな後押しになります。
「無理しなくていいよ」「外に居場所をつくっても大丈夫だよ」
という言葉は、想像以上に力を持っています。
こうして世界を広げる選択肢を見つけていくことで、
子どももあなた自身も、「この先にまだ道はある」と安心できるようになります。
高校で「友達はいるけど楽しくない」とき、子どもの自立を育てる親の関わり方
行き渋り・不登校になる前にできる声かけ——事実を聞き、感情に共感し、選択肢を一緒に考える

高校がしんどくなると、朝の支度が遅くなったり、「今日は休みたい」とつぶやく回数が増えてきたりします。
そんなとき、親がどんな声をかけるかで子どもの気持ちは大きく変わります。
特に、「高校 友達いるけど 楽しくない」と感じている子は、
行き渋りに発展しやすいからこそ丁寧な関わりが大切です。
まず意識したいのは、いきなり理由を追及しないことです。
「なんで行かないの?」と聞かれると、子どもは責められたように感じてしまいます。
そうではなく、“事実を静かに聞く”ことから始めましょう。
「今、どんな感じ?」「今日は体が重いのかな?」など、
子どもの状態をそのまま確認する言葉が安心につながります。
次に必要なのは、感情への共感です。
「そっか、しんどいって感じるんだね」「行く気になれない日もあるよね」と、
子どもが抱えている気持ちに寄り添うこと。たったこれだけで、
子どもは「わかってもらえた」と感じ、心がほどけていきます。
たとえ理由がうまく言えなくても、その曖昧さごと受け止めてあげて大丈夫です。
そして落ち着いてきたら、選択肢を一緒に考える段階へ進みます。
「今日は遅れて行く?」「保健室から入る?」「担任の先生に相談してみる?」と、
子どものペースに合わせて“複数の道”を示してあげてください。
選択肢が見えると、子どもは「全部がイヤ」という感覚から抜け出しやすくなります。
ここで重要なのは、答えを押しつけないことです。
選ぶのは子ども自身です。親は“道しるべをそっと置く”だけで十分。
自分で選んだという感覚は、子どもの自立と自己効力感を大きく育てます。
行き渋りの初期は、親の落ち着いた関わりが何よりの支えになります。
「話してくれてありがとう」「一緒に考えようね」という姿勢が、
子どもにとっての安心基地となり、
学校との距離の取り方も自然に整っていきます。
こうした関わりを続けることで、あなた自身も「焦らなくていい」という感覚を取り戻し、
次に進む道筋が見えてくるはずです。
家庭学習を「小さな成功体験」の場に——高校が楽しくない子の自己肯定感と自立を支える
高校生活がしんどいとき、子どもは自信を失いやすくなります。
とくに、「高校 友達いるけど 楽しくない」と感じている状態が続くと、
「自分って何もうまくいかないのかな…」という思い込みが強くなり、
心がどんどん縮こまってしまいます。そんな時期こそ、家庭学習は“心の回復”に役立つ大切な場所になります。
ここで大事なのは、テストで高得点を取らせることではありません。
目指すのは、“小さな成功体験”を積み重ねることです。
たとえば、「昨日より1問多く解けた」「今日は10分だけでも机に向かえた」「英単語を3つ覚えられた」
——そんな小さな前進で十分なのです。
高校が楽しくない子は、学校の中で成果を感じにくくなっているため、自分を肯定する材料が不足しています。
だからこそ、家庭での小さな成功が、心の支えになります。
親が「よくやったね」「ちゃんと進んでるよ」と声をかけるだけで、
子どもの自己肯定感は少しずつ戻っていきます。
さらに、家庭学習は“自立の練習の場”にもなります。
「自分で決めて、自分のペースでやる」という経験は、学校でのストレスとは別軸の自己効力感につながります。
これが育つと、子どもは学校の人間関係や環境に振り回されにくくなります。
取り組み方のポイントは、
・短時間でいい(10〜20分で十分)
・やる内容はシンプルに
・達成できたら、必ず言葉で認める
この3つだけでOKです。
特に、最初から欲張らないことが大切です。
子どもが負担なく続けられる形が一番効果的です。
そして親として心に留めておきたいのは、家庭学習は“追い詰めるため”ではなく、
“回復と自立のため”ということです。あなたの温かい見守りが、
小さな成功体験を確かな力に変えていきます。
こうした積み重ねによって、子どもは「自分でできることがある」と感じられるようになり、
あなた自身も「この方向でいいんだ」と未来への安心が少しずつ広がっていきます。
高校で「友達はいるけど楽しくない」と言う我が子に、親ができること:まとめ
高校で「友達はいるけど楽しくない」と感じるのは、決して珍しいことではありません。
むしろ、思春期の心の成長や環境の変化が重なる時期だからこそ、多くの子が同じ壁にぶつかっています。
ここまで見てきたように、理由はひとつではなく、
人間関係・学校の雰囲気・プレッシャー・目的の揺らぎなど、いくつもの要因が重なっているのです。
まずは、あなたの子どもが感じているしんどさを
「わかるよ」と受け止めてあげることが、何よりの支えになります。
そして、学校の中だけで解決しようとしないことも大切です。
部活、アルバイト、家庭、オンラインなど、学校以外の場所に“小さな安心”をつくることで、
気持ちの回復力は大きく変わります。また、家庭学習の中で小さな成功体験を積むことは、
自信を取り戻す大きな助けになります。「自分でもできることがある」という感覚は、
子どもを再び前に進めてくれる力になります。
親としての関わり方で大切なのは、急がないこと、焦らないこと、決めつけないことです。
「どうしたらいいの?」と不安になってしまう気持ちもわかりますが、
子どものペースを尊重しながら、寄り添っていく姿勢こそが、一番の安心になります。
最後に、あなたにも伝えたいことがあります。
——この悩みは、必ず出口があります。
——子どもは着実に成長しています。
——今のあなたの関わりは、間違っていません。
今日の記事を読んで、「次にどう動けばいいか」が少し見えてきたなら、それだけで十分です。お子さんにも、あなたにも、これからの毎日に“ほどよい光”が差し込んでいきますように。