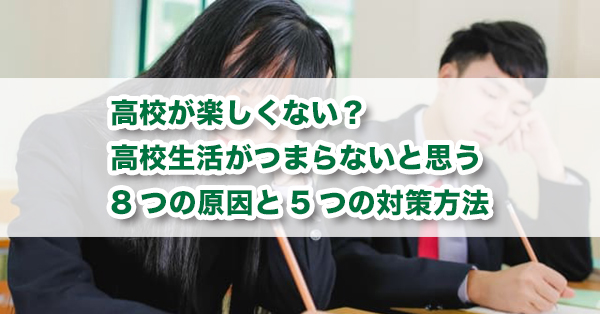高校を楽しくないと感じる割合はどれくらい?“約1〜3割”の子どもを自立に導く親の関わり方
「高校が楽しくないみたいで心配…」「うちの子だけ特別なの?」——そんな不安から「高校 楽しく ない 割合」を検索する保護者はとても多いです。実は、統計を見ると“高校が楽しくない”と感じている生徒は約1〜3割ほど。決して珍しいことではありません。しかし、数字を知るだけでは安心できないのも親心ですよね。本記事では、元教師の視点から「なぜ高校が楽しくないのか」「不登校や退学につながるサイン」「家庭でできる支え方」までを丁寧に解説します。最後には、子どもが自立へ向かう小さな一歩——家庭学習の大切さについても触れていきます。
高校 楽しく ない 割合はどれくらい?データで見る“約1〜3割”は決して珍しくない
この章のポイント
- 高校が楽しくないと感じる割合は約1〜3割で、決して珍しくない。
- 理由は人間関係・部活・勉強・校風など複数が重なるケースが多い。
- 楽しめない期間は一時的で、時間と環境で改善することも多い。
- 大切なのは“割合”よりも、目の前の子どものしんどさに気づくこと。
- 保護者の寄り添いが、気持ちの安定と次の一歩につながる。
統計から見る「高校 楽しく ない 割合」——約1〜3割の高校生が高校生活に満足していない

「高校が楽しくない割合って、実際どれくらいなんだろう…?」——そう感じたことはありませんか。
データを見ると、高校生活を“楽しくない”と答える生徒はおよそ1〜3割。
決して少なくはない数字です。
むしろ、子どもが抱える「なんとなくつらい」「周りに合わせられない」
という感覚は、多くの高校生が経験しているものだと言えます。
とはいえ、「3割もいるなら安心していいの?」と感じる方もいるでしょう。
ここで大切なのは、割合そのものよりも、
お子さん自身のしんどさに気づけているかどうかです。
高校生活は友人関係、部活、学業、
将来への不安など、環境の変化が一気に重なる時期。
誰にとっても負担が大きく、特に真面目で頑張り屋の子ほど
「楽しくない」と感じやすい傾向があります。
あなたのお子さんは、最近どんな表情をしていますか?
「友達関係の話をしなくなった」
「学校の出来事を聞かれるのを嫌がる」
「朝の用意が遅くなった」
——そんな小さな変化も、“高校が楽しくない割合”の中に含まれる
子どもたちが見せやすいサインです。
一方で、高校が楽しくないと感じたからといって、
すぐに不登校や退学につながるわけではありません。
むしろ、本音を言える相手が一人でもいれば、
気持ちは驚くほど軽くなります。
ですから、まずは「そう感じる時期は誰にでもあるよ」
と寄り添うことが、お子さんにとって大きな安心になります。
そして、保護者であるあなたがこの割合を知る意味は、
“うちの子だけが特別に悩んでいるわけじゃない”と気づくことです。
数字に振り回される必要はありませんが、
裏側には多くの高校生が抱えている
共通のしんどさがあります。
この現実を知ることで、気持ちが少し軽くなり、
「次に何をサポートすれば良いか」も見えるようになってきます。
高校が楽しくない割合が1〜3割という数字は、お子さんの未来を決めるものではありません。
むしろ、今の気持ちに気づき、寄り添えるチャンスでもあります。
あなたがその第一歩を踏み出すことで、お子さんは“自分らしさ”を取り戻し、
これからの高校生活に新しい選択肢を見出していけるはずです。
「高校生活は人生で一番楽しい」という言葉にしんどくなる子どもたち
「高校生活は楽しいはず……なのに、なぜうちの子はそう感じられないんだろう?」
そんな疑問を抱く親御さんは少なくありません。
実際に調査結果を見ると、“高校が楽しくない”と答える高校生は全体の1〜3割ほど。
この高校が楽しくない割合は決して小さな数字ではなく、
多くの子どもが似たような悩みを抱えています。
とはいえ、「3割いるなら普通のこと」と安心していいわけでもありません。
割合よりも大切なのは、
お子さんが“今、どんな気持ちで高校生活を過ごしているのか”です。
高校は人間関係・勉強・進路の悩みが一気に押し寄せる時期。
真面目で責任感が強い子ほど、「上手くいかない自分」を責めてしまい、
楽しさを感じづらくなってしまうものです。
たとえば最近、お子さんの様子にこんな変化はありませんか?
「学校の話をしなくなった」「表情が沈みがち」「休みの日にほっとしている」
これらは、“高校が楽しくない割合”に含まれる子が見せやすいサインです。
もちろん、一時的に気分が落ち込むのは自然なことですが、
続くようであれば丁寧に話を聞くタイミングかもしれません。
そして忘れてはならないのは、高校が楽しくない=将来が暗い
ということでは決してない、という点です。
高校生活が合わなかったとしても、その子の人生全体を左右するわけではありません。
むしろ、「楽しめない自分」を認め、無理しすぎない環境を作れる子は、
長い目で見ると自立しやすい傾向にあります。
保護者としてできることは、「なんで楽しくないの?」と原因追及をするよりも、
“その時の気持ちを否定せず受け止めること”です。
あなたが寄り添うことで、「話していいんだ」とお子さんが感じられ、
また一歩前に進む力になります。
高校が楽しくない割合が1〜3割という数字は、お子さんを不安に感じる材料ではなく、
「同じ気持ちの子はたくさんいるよ」という安心材料として役立ちます。
この現実を知っているだけで、あなた自身の気持ちもスッと軽くなり、
「この先どう見守ればいいのか」が見えてくるはずです。
「うちの子だけ?」と不安な保護者へ——割合より大切なのは“今のしんどさ”に気づくこと

「高校が楽しくない割合が1〜3割なら、うちの子もその中に入っているだけなのかな…」
そう思おうとしても、どこか胸がざわつく——そんな気持ち、ありませんか。
実際、多くの親御さんが「うちの子だけ?」という不安を抱えています。
でも、本当に大切なのは割合そのものではなく、
“お子さんが今どれだけしんどさを抱えているか”に気づいてあげることです。
たとえば、最近お子さんの表情に変化はありませんか?
・急に無口になった
・学校の話題を避ける
・休日にぐったりしている
・朝の支度に時間がかかる
こうした小さなサインは、数字では測れない“心の重さ”を映し出しています。
高校が楽しくない割合の中に入るかどうかではなく、「今、つらい気持ちを抱えているか」が本質です。
私が学校で見てきたのは、しんどさを我慢し続けてしまう子ほど、
親に「大丈夫」と言う傾向が強いということです。
だからこそ、保護者が気づいて声をかけてあげることが何よりの支えになります。
「無理して笑わなくていいよ」「話したくなったらいつでも聞くよ」
——そんな小さなひと言が、驚くほど子どもの心を軽くします。
反対に、割合ばかりに意識が向くと、気持ちを見落としてしまうことがあります。
「みんな悩む時期なんだから」「3割もいるなら普通でしょ」
そんな言葉は、結果的にお子さんの本音を
閉じ込めてしまうことにもつながりかねません。
だからこそ、意識してほしいのは、「うちの子が“今”どう感じているか」です。
その小さな変化に気づける親であることは、誰よりも大きな支えになります。
高校生活が楽しくないと感じることは、決して特別なことではありません。
でも、そのしんどさに寄り添えるのは、保護者であるあなたしかいないのです。
「高校が楽しくない割合」がどうであれ、あなたが気づいてくれること
——それが、 お子さんが次の一歩を踏み出す力になります。
そして、その気づきが、これから親子で“どう進むか”を見つけていくスタートになるのです。
高校が楽しくない理由とリスク——人間関係・部活・勉強プレッシャーと「行きたくない」のサイン
高校生活が楽しくない主な理由——友達・グループ・部活動・校風・通学・勉強のプレッシャー

「どうして高校生活が楽しくないんだろう?」 そう感じるお子さんは決して少なくありません。
実際、高校が楽しくない割合は1〜3割程度といわれていますが、
その裏には“理由が一つではない”という現実があります。
高校は急に環境が広がり、人間関係・勉強・生活リズムの変化が同時に押し寄せる時期。
真面目な子ほど、その負担を自分一人で抱え込んでしまいがちです。
まず最も多いのは、友達やクラスのグループに馴染めないケースです。
中学とは違い、友達がバラバラになり、輪の作り方も大人びてきます。
「話が合わない」「気を遣いすぎて疲れる」という声はよく聞かれます。
あなたのお子さんはどうでしょうか? 以前よりも
クラスや友達について話さなくなってはいませんか。
次に、部活動の人間関係や雰囲気が合わないことも大きな要因です。
先輩後輩の関係、指導の厳しさ、仲間の空気感——部活は生活の大部分を占めるため、
うまくいかないと「学校=つらい場所」と感じやすくなります。
努力家の子ほど「辞めたいと言えない」「迷惑をかけたくない」と抱え込んでしまうことも。
さらに、「校風が合わない」という理由もあります。
自由すぎて合わない、逆に校則が厳しすぎて息苦しい
——どちらも子どもにとってはストレスになり得ます。
長時間の通学や満員電車がしんどく、毎日学校に行くだけでエネルギーを
消耗してしまうケースも珍しくありません。
そして見逃せないのが、勉強のプレッシャーです。
高校では授業スピードが速くなり、「ついていけない」「成績が下がって自信をなくす」
という子が一気に増えます。
進路への不安も重なるため、「何を頑張ればいいのかわからない」
と気持ちが追いつかなくなるのです。
こうした複合的な要因が積み重なることで、
“高校が楽しくない割合”に含まれる子どもたちが
支えを必要とする状況になります。
ただ、どの理由も「弱さ」ではありません。
環境の変化が激しい高校生活では、ごく自然な反応です。
大切なのは、親が「理由を決めつけず、気持ちに寄り添う姿勢を持つこと」。
お子さんが抱える原因は一つではなく、「少しずつ積み重なったしんどさ」であることがほとんどです。
その重さに気づき、そっと寄り添うことが、これからの選択肢と希望につながっていきます。
「高校つまらない・行きたくない」ときに出るサイン——中学に戻りたい・休みたがる毎日の裏側
「最近、なんだか元気がない」「前より笑わなくなった」
そんな小さな変化に気づいたとき、もしかするとお子さんは“高校つまらない・行きたくない”
という気持ちを抱えているのかもしれません。
データを見ると、こうした悩みを抱える子は高校が楽しくない割合1〜3割
に含まれると言われています。
でも、その気持ちは数字では測れないほど繊細で、
言葉にできないまま心の中にしまい込まれがちです。
たとえば「中学に戻りたい」という言葉。
一見、昔の友達が恋しいだけに見えますが、
実は「今の環境がしんどい」「中学のほうが安心できた」
というサインでもあります。
あなたのお子さんは、ふとした瞬間にこんな言葉を漏らしていませんか?
また、朝になると「頭が痛い」「お腹が痛い」と訴える日が増えることもあります。
これは身体の不調というより、心のストレスが表に出ていることが多いのです。
休みたがる理由を深掘りしようとすると、
子どもは黙り込んでしまうことがありますが、その沈黙こそ、
高校が楽しくない割合の中に入る子が見せる“助けて”のサインです。
さらに、こんな行動も気づきの手がかりになります。
・帰宅後、すぐに部屋にこもる
・休日は何もしたくないと言う
・学校の話題を避ける
・提出物やテスト勉強に手がつかない こ
れらは「サボっている」のではなく、
心のエネルギーが足りていない状態。頑張り屋の子ほど、
「つまらない」「行きたくない」と口にすることさえできません。
大切なのは、「行きたくないと言わない=元気」という判断をしないことです。
むしろ、言えない子どものほうが多く、
親が気づけるかどうかでその後の流れが大きく変わります。
あなたが思った以上に、お子さんは“本音を言うことで
迷惑をかけたくない”と考えています。
もし、あなたが「最近、しんどそうだな」と感じているなら、
それは立派なサインの受け取り方です。
「無理しなくてもいいよ」「何があったか、ゆっくりでいいから教えてね」
そう声をかけるだけで、お子さんは“味方がいる”と感じられます。
高校が楽しくない割合の1〜3割に入っていたとしても、それは決して珍しいことではありません。
でも、あなたの気づきが、しんどさが深くなる前にブレーキをかける力になります。
そして、その気づきこそが、高校生活をこれからどう整えていくかを
一緒に考えるための大切なスタートになるのです。
転校・通信制高校・フリースクール…「続ける/変える」の選択肢をどう見極めるか

「このまま高校を続けて大丈夫なんだろうか…」「転校や通信制を考えるべき?」
お子さんがつらそうにしていると、保護者としてどう判断すれば良いのか迷いますよね。
実際、高校が楽しくない割合は1〜3割と言われ、
一定数の子どもが“続けるか/環境を変えるか”という岐路に立ちます。
ただ、その選択に正解はひとつではありません。
大切なのは、“今のお子さんの状態”に合った選択を見極めることです。
まず考えたいのは、「続ける」という選択。
高校生活には、時間とともに人間関係が落ち着いたり、
授業に慣れてきたりと、“自然に好転していくタイミング”が必ずあります。
・しんどさが一時的
・友人関係が安定しつつある
・先生や相談できる大人がいる
こうした状況なら、急がず見守ることが子どもにとって良い場合も多いです。
一方で、「変える」選択が必要になるケースも確かにあります。
・登校しぶりが続く
・心や身体の不調が長引く
・教室に入るだけで強い抵抗がある
・高校の校風が根本的に合わない
こうした場合、無理に続けると自己肯定感が下がり、
さらに学校が苦手になる可能性があります。
ここで“合わない環境を変える”ことは、決して逃げではありません。
むしろ、視野を広げるきっかけになります。
転校には、全日制高校への編入だけでなく、
通信制高校・定時制高校という選択肢があります。
通信制は自分のペースで学べるため、心の余裕を取り戻しやすい子も多く、
登校負担が小さいのが特徴です。
また、フリースクールや教育支援センターなど、
学校と社会の“間”で過ごせる場所も増えており、
学校に通えない時期の大切な居場所になります。
ここで重要なのは、“続ける”と“変える”を白黒で選ばないこと。
「まず保健室登校から始める」
「別室登校で負担を減らす」
「週1から通信制に通う」
このように、どちらか一方ではなく、段階的な選択も可能です。
今のお子さんの体力・気力に合わせて、
一番無理のない道を選んでいくことが未来につながります。
最後に、保護者としてできるもっとも大切なことは、 “どの選択をしても大丈夫だよ”と伝えることです。
高校が楽しくない割合に入っていたとしても、それはその子の価値を下げるものではありません。
むしろ、今のしんどさを自覚し、環境を整えることができるのは、
大人になる上で大きな力になります。
続けるにせよ、変えるにせよ、お子さんが「自分で選べた」と感じられる道を一緒に探していくこと。
それが、これからの高校生活を前向きに再スタートさせるための大きな一歩になるのです。
高校 楽しく ない 割合の子どもをどう支える?——家庭での関わり方と家庭学習が「自立」の土台になる
「高校3年間が楽しくなかった」経験を“失敗”で終わらせない親の声かけ

「高校3年間が楽しくなかったなんて…このまま失敗のまま終わってしまうんじゃないか」
保護者として、そんな不安が胸に広がることはありませんか。
でも、覚えておいてほしいのは、“高校が楽しくない割合は1〜3割”といわれ、
決して珍しいことではないという現実です。
そしてもうひとつ──高校生活が楽しくなかったことは、
その子の人生の失敗でも評価でもないということです。
むしろ大切なのは、ここからどう気持ちを立て直し、
未来に向けて動き出せるか。 そのために必要なのは、
保護者であるあなたの声かけです。
たとえば、こんな言葉をかけてみてはどうでしょうか。
「3年間、よく頑張ったね」
「楽しくなかったって言えるのは勇気がいるよ」
「合う・合わないは誰にでもあるよ」
こうした言葉は、“結果”ではなく“過程”を認めるメッセージ。
高校が楽しくなかった自分を責めている子にとっては、大きな救いとなります。
逆に、「どうしてもっと頑張れなかったの?」「みんな楽しんでいたのに」など、
他者比較を含む言葉は避けたほうが安心です。
子どもは自分が十分努力できなかったと感じていることが多く、
責められるとさらに心を閉ざしてしまいます。
そして忘れてはならないのは、“高校が楽しくない経験”は、必ずしもマイナスではないということ。
合わない環境を知れたこと、気持ちの限界に気づけたこと、
自分に向いていないことが見えたこと
──これらは大人になってからの選択に確実に活きてきます。
高校時代、楽しくなかった子ほど、大学や社会に出て
「自分らしい場所」を見つけて大きく成長するケースも少なくありません。
あなたの声かけの目的は、過去を変えることではなく、
“これからの道を歩きやすくしてあげること”です。
「楽しくなかった高校生活」は人生のひと区切り。それ以上でも以下でもありません。
ここからどう未来を描くか、その背中をそっと支えられるのは、
保護者であるあなたの言葉だけです。
高校が楽しくない割合の中にいたとしても、
そこで終わりではありません。
むしろ、そこから新しいスタートが始まります。
あなたの優しい一言が、お子さんの“これから”を前向きに変える力になるのです。
学校以外のコミュニティ・趣味・アルバイト——高校生活が楽しくなくても世界を広げる方法
「学校がしんどそう…でも、この子の世界が学校だけで決まってしまうのは違う気がする」
そんなふうに感じたことはありませんか。
実は、高校が楽しくない割合は1〜3割といわれ、
学校生活だけでは満たされない子は決して少なくありません。
だからこそ、“学校以外の世界”を持てるかどうかが、
その後の自信や自己肯定感に大きく影響します。
たとえば、趣味の世界。 絵、音楽、ダンス、読書、プログラミング、写真
…学校では出会えなかった「好きなこと」に没頭できる場所は、
心のエネルギーを回復させてくれます。好きなことを通してできた友人は、
クラス内の関係とは全く違い、無理をせず自然体で過ごせることが多いのです。
あなたのお子さんにも、ずっと続けてきたことや、
ほんの少し興味を持っていることはありませんか?小さなきっかけでも十分です。
また、オンラインコミュニティも大きな味方になります。
今は部活に合わなくても、SNSやオンラインサークル、
地域のワークショップなどで「価値観の近い人」とつながることが可能です。
狭いコミュニティしか知らないまま悩んでしまうより、
外の世界を知ることで「この環境だけがすべてじゃない」と気づけることは、
精神的な安心につながります。
さらに、アルバイトも世界を広げる有力な選択肢です。
学校では会わない年代の人と関わったり、仕事を通して自分の役割を持てたりする経験は、
お子さんにとって大きな自信になります。
「ここでは自分を必要としてくれる人がいる」
そんな感覚は、学校で感じられなくても、
社会の中で出会えることがあります。
そして、これらの経験がなぜ大切なのかというと、
“自分の居場所は一つじゃない”と思えることが、
心の安全基地になるからです。高校が合わなかったとしても、
外の世界に居場所が見つかれば、「学校がすべてじゃない」と前を向けるようになります。
これは、高校が楽しくない割合に入る子たちにとって、非常に大きな救いになり得ます。
保護者としてできるのは、学校以外の選択肢を“逃げ”と見なさない空気をつくることです。
「こんな場所もあるよ」「無理しなくていいよ」 そんな声かけがあるだけで、
お子さんは安心して自分の世界を探しに行くことができます。
高校生活が楽しくなくても、人生の選択肢は無限に広がっています。
むしろ、早くから「学校以外の世界」を知ることは、
これからの自立につながる大切な財産になるのです。
家庭学習の重要性——毎日の小さな勉強習慣が自己肯定感と自立心を支える

「高校が楽しくないみたいで心配…でも、勉強のことまで口出しすると負担をかけてしまうのでは?」
そんな思いから、家庭学習への関わり方に迷う保護者はとても多いです。
けれど実は、高校が楽しくない割合(1〜3割)に入る子ほど、
“毎日の小さな家庭学習”が心の支えになることをご存じでしょうか。
ここでいう家庭学習は、長時間の勉強ではなく、たった10〜15分の「コツコツ続けられる習慣」のことです。
なぜそれが大切なのかというと、学校生活がうまくいかないと、
自信が揺らぎやすくなるからです。
友達関係、部活の疲れ、プレッシャーのある授業……高校が楽しくない状態が続くと、
「自分ってダメなのかな」と自己肯定感が下がりがちになります。
その時に、「今日も10分だけ続けられた」「昨日より単語が覚えられた」
という小さな成功体験が、心を支える土台になるのです。
特におすすめなのは、英語の家庭学習です。
英単語・短いリスニング・音読などは、短時間で成果を感じやすく、
学校外でも取り組みやすい分野。 「1日たった10分でいいなら、やれるかも」
そう思えるハードルの低さが、継続につながります。
そして、積み重ねた経験は「自分でもできる」という自己効力感となり、
高校が楽しくない時期を乗り越えるための大切な自信になります。
家庭学習は、成績を上げるためだけのものではありません。
むしろ、気持ちが不安定なときに生活のリズムを支える“軸”のような存在になります。
10分の勉強があることで、一日の中に「整う時間」が生まれ、
気持ちが乱れやすい高校時代にちょっとした安定をもたらしてくれます。
あなたができるサポートは、厳しく見張ることではなく、 「今日の10分ができたね」「続けてるのすごいね」と小さな努力を認めること。 子どもは褒められたいわけではなく、「見てくれている」という安心がほしいのです。
高校が楽しくない割合に入っていたとしても、小さな積み重ねができる子は必ず強くなります。 高校生活がうまくいかなくても、家庭学習という日々の基盤が、未来の選択肢と自立につながっていきます。 あなたの優しい見守りが、思った以上にお子さんを前に進ませる力になるはずです。
高校 楽しく ない 割合はどれくらい?“約1〜3割”の子どもを自立に導く親の関わり方:まとめ
高校が楽しくないと感じる高校生は、調査によるとおよそ1〜3割。
この“高校 楽しく ない 割合”という数字は、決して特別でも異常でもありません。
むしろ、多くの子が人間関係・勉強・校風・生活リズムなどの壁にぶつかりながら、
それでも毎日をなんとか乗り越えています。
大切なのは、数字で安心しようとすることではなく、
“目の前のお子さんが今どう感じているか”に寄り添う姿勢です。
「高校つまらない」「行きたくない」という言葉の裏側には、不安・緊張・疲労・孤独など、
子ども自身が言葉にできない思いが隠れています。その気持ちに気づき、
受け止めてあげることが、どんな支援よりも先に必要な一歩です。
また、高校生活がうまくいかなくても、人生の選択肢が狭まるわけではありません。
趣味やコミュニティで世界を広げたり、アルバイトで新しい人間関係に触れたり、
通信制・転校など環境を見直す選択肢もあります。
高校が合わなかったからこそ、
新しい道を見つけて大きく成長する子はたくさんいます。
そして、お子さんが未来へ向かう力になるのは、
家庭での小さな積み重ねです。 1日10分の家庭学習でも、
“できた”を積み上げることで自己肯定感が育ち、
「自分にも続けられることがある」 という感覚は、
つらい時期を支える大きな柱になります。
高校が楽しくない割合に入っていたとしても、
それは“終わり”ではなく、“自立への入り口”です。
親であるあなたが、数字ではなく気持ちを見つめ、
声をかけ、日々の小さな努力を見守ってあげれば、
お子さんは必ず自分のペースで前に進んでいけます。
高校生活がどうだったかよりも、これからどう生きていくか。
その未来を支えるのは、あなたのそばにある小さな気づきと、やさしい関わりです。