高校の留年はいつわかる?進級判定のタイミング・基準・回避策を元教師がやさしく解説
高校生活は、子どもの「自立への一歩」として見守りたいものですよね。だからこそ、欠席が増えたり成績が下がったりすると、「もしかして留年…?」と胸がざわつくのは当然です。
私も学校で多くの親子に寄り添ってきましたが、留年は“突然”決まるものではありません。そこには必ず兆しと、まだできる手立てがあります。いま不安を抱えているあなたと一緒に、状況を整理し、前に進む道を考えていきましょう。
進級判定会議は2〜3月ごろ。最終決定はこの段階で出る

2〜3月の「進級判定会議」で最終決定——高校の留年はいつわかる?通知はいつ来る?
結論から言うと、高校で留年がいつ決まるかの“最終ライン”は、2〜3月ごろに行われる進級判定会議です。ここで、各科目の 単位修得状況・出席・成績・提出物・生活記録 が総合的に確認され、進級か留年かが正式決定します。
ただし、「留年はこの日だけで決まる」わけではありません。
実際には、その前の数か月間の積み重ねによって、結果はかなり見えてきます。
では、なぜこの時期に判定されるのでしょうか。
理由は、成績の確定・追試や補習の結果・出席日数の最終集計が揃うタイミングだからです。
高校では、単位認定が進級条件の基本です。
そのため、科目ごとの成績評価が終わり、補習や追認課題を提出し終え、出席日数を確定させたあとでなければ、公平な判断ができません。
つまり、
「進級判定会議=突然の宣告の日」
ではなく、
「その前から、サインは静かに積み重なっている」
ということです。
では、高校で留年がいつ決まるのかを、もっと 体感的 に考えてみましょう。
- 2学期の後半:成績や欠席の傾向が見えてくる
- 冬休み〜3学期初め:補習・追試・追認の機会
- 2月上旬:科目の最終評価が固まる
- 2月下旬〜3月中旬:進級判定会議 → 最終決定
こうして並べると、
「学年末に突然決まる」のではなく、「秋〜冬の時点で流れは形成されている」ことがわかります。
ここで大事なのは、
「まだ間に合う段階で気づく」こと。
なぜなら、
留年は“結果”であって、“いきなりの出来事”ではないからです。
もし今、
- 欠席が増えている
- 補習の案内が来ている
- 成績が伸び悩んでいる
- 学校から連絡が増えている
こうした状況があるなら、
すでに 大切なサイン は出ています。
不安になるのは当然です。
けれど、早く知れたことは悪いことではありません。
「今からできることを整えられる」からです。
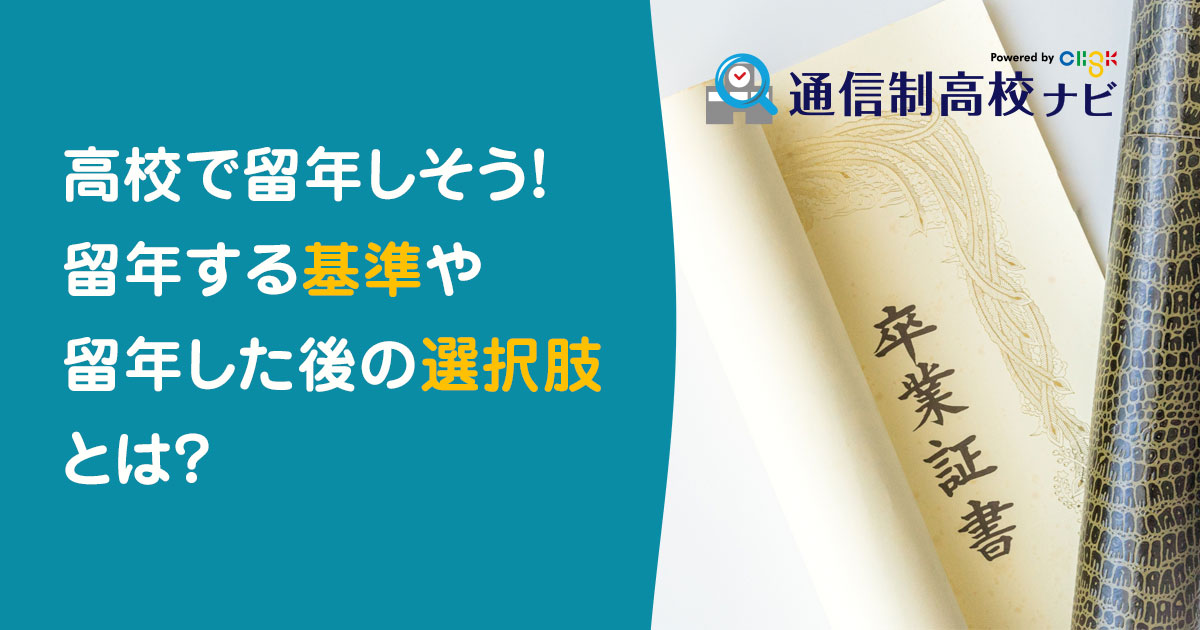
では、具体的に今できることは?
- 担任に「現時点の進級見込み」を確認する
→ 「留年の可能性はありますか?」と聞いてよい質問です。 - 科目別に“危険科目”を可視化する
→ 英語・数学・国語など基幹科目は特にチェック。 - 出席・提出・小テストの管理を“週単位”に落とす
→ 1日単位ではなく、1週間で見ると改善が続きやすい。
高校生活は、やり直しが利かないように見えて、
実は 「いま動けば間に合う構造」 で作られています。
出席不足は“その時点で”留年がほぼ確定することも
高校では出席不足が起きた段階で、留年が“その時点でほぼ確定”することがあります。
ここが、成績不振の救済(補習や追試)と大きく違うところです。
成績は後から巻き返すルートがありますが、出席は「授業に出ていたか」という事実が重視されるため、後から取り戻すことが難しいのです。
では、高校の留年はいつ決まるのでしょうか。
最終的には、2〜3月の進級判定会議で決まります。
けれど、出席不足に限っては、もっと早い段階で“実質的に結果が見えてしまう”ことが多いのです。
多くの高校では、「授業時数の3分の2以上の出席」が、単位認定の最低条件として定められています。
このラインを下回ると、成績がどれだけ良くても単位は認定されません。
つまり、単位が取れない → 進級に必要な科目が揃わない → 留年に直結するという流れです。
これが「出席不足は“その時点で”留年がほぼ確定すると言われる理由」です。
ここで、少し視点をやわらかくして整理しましょう。
- 「今日は行きたくない」が数回
- 朝起きられない日が少し続く
- 体育や人間関係で学校が重くなる
どれも「よくあること」です。
責める必要はありません。
ただ、それが 週単位 → 月単位 になっていくと、
出席の累積は想像以上にスピードを持って増えていきます。
気づいたら「あと2回休んだらアウト」というラインまで来ている、というのは本当に多い。
だからこそ、
“いまどれくらい足りているか”を可視化することが、いちばんの防波堤です。
今日できること(かんたんで現実的)
- 担任に「科目別の出席状況」を確認する
→ 「あと何回まで大丈夫ですか?」は、聞いていい質問です。 - 遅刻・早退の換算ルールを知る
→ 「遅刻3回で欠席1回扱い」など、学校ごとに違います。 - 朝の負担を減らす工夫を優先する
→ 勉強より先に“生活リズム”を整えるほうが効果が出ます。 - 週単位の出席管理表をつくる
→ 毎日ではなく「週で見る」と気持ちが楽です。
そして何より伝えたいのは、
「休んだからダメな子」ではないということ。
学校がしんどい時期があるのは普通です。
体と心には波があります。
大切なのは、苦しくなる前に“手を取って一緒に立て直せる”ことです。
高校の留年がいつ決まるかという情報は、
「不安を深めるため」ではなく、
“まだ間に合ううちに気づくため”の地図として使ってください。
あなたとお子さんは、まだ間に合っています。
今、気づけているということが、すでにとても大きな一歩です。
成績不振は「補習→追試→追認指導」を経て最終判断される

成績が思うように伸びなかったとき、高校ではすぐに留年が確定するわけではありません。
ここが、出席不足の場合と大きく違う点です。
実際には、補習 → 追試 → 追認指導(レポートや再試験など) と、段階的に 巻き返すチャンス が用意されています。
つまり、“赤点がついた=もう終わり”ではないということです。
では、高校の留年はいつ決まるのか?
答えは、2〜3月に行われる進級判定会議で正式に決まります。
しかし、成績不振に関しては、その前の「このチャンスをどう使うか」でほぼ結果が見えていくのです。
ここで、成績不振の流れを具体的に整理してみます。
1)補習
授業内容の復習や、単元ごとの理解確認が行われます。
ここで「わからないまま流す」と、次が苦しくなります。
2)追試(再テスト)
定期テストで基準点に届かなかった科目を再度評価する機会です。
この段階での“粘り”がとても大きい差になります。
3)追認指導(レポートや追加課題など)
追試でも基準に届かない場合、単位認定の最終ラインとして出されます。
提出期限・記述量・表現方法など細かい指定があることが多く、ここは誠実さと継続力が問われます。
では、なぜこのプロセスが重要なのか。
それは、「やり直せる力があるか」を学校は見ているからです。
単に点数が良いか悪いかだけではなく、
- わからないところに向き合う姿勢
- 課題に期限内で取り組む継続力
- 先生に相談する主体性
これらこそが、高校で生きる力であり、進級判定の中でとても重視されます。
ここが “留年はいつ決まるか”が「結果ではなくプロセスで決まっていく」 と言われる理由です。
とはいえ、
「うちの子、追試や課題になると手が止まってしまうんです…」
という声は本当に多いです。
そしてそれは、怠けているからではありません。
多くの場合、
- うまくできなかった経験が重なり、自信が削れている
- “何から手をつければいいか” が整理されていない
- 完璧にしようとして、逆に動けなくなる
という 心の疲れ が背景にあります。
そこで、成績不振のときの親の関わり方で大切なのは、
「やりなさい」ではなく、「一緒に分けよう」 です。
今できる具体的なサポート(現実に効果が出る形)
- 課題・追試の日程をカレンダーで“見える化”
- 科目ごとに「今日やるのはここだけ」と範囲を小さくする
- できたら1つだけ必ず“言葉で認める”
例:「そこできたの、ちゃんと見てるよ」
これは、勉強の助けではなく、心が動ける土台をつくる行為です。
まとめると。。。
- 高校の留年は 2〜3月の進級判定会議で正式に決まる
- ただし 成績不振は「補習→追試→追認指導」で十分に巻き返せる
- 判断は 点数より“向き合う姿勢”が強く影響する
- いまできることは、範囲を小さくして、一緒に動き始めること
いま「どうしよう」と思えているあなたとお子さんは、まだ間に合っています。
焦らなくていい。
でも、止まらなくていい。
一歩ずつ、ここからで大丈夫です。

高校で留年が決まる基準とは?出席・単位・課題の3つが核
単位認定の基本は「授業の2/3以上の出席

高校で進級できるか、留年になるかを左右する大きな軸の一つが、「出席状況」です。
多くの高校では、授業の出席が“3分の2以上”あることが、単位認定の最低条件とされています。
これは全国的に広く採用されている基準で、成績がどれだけ良くても、出席が足りなければ単位は認められないという厳しいルールです。
「うちの子、テストはそこまで悪くないんだけど…」
「成績は平均は取れてるのに留年の話が出たの?」
という相談は、とても多いです。
その理由は、
高校の留年は“成績”だけで決まるわけではない
からです。
では 高校の留年はいつ決まるのか?
最終的には、2〜3月に行われる進級判定会議で決まります。
けれど、出席不良が溜まっている場合は、その前から“ほぼ結果が見えてしまう”ことが多いのです。
出席は「過去にさかのぼって増やす」ことができません。
そのため、
- 欠席の累積
- 遅刻早退の換算ルール
- 保健室登校の扱い
- 長期欠席の理由書提出
こういった要素が徐々に積み重なり、あるタイミングで「あと〇回でアウト」という現実が突然目の前に現れます。
この「ラインが見えた瞬間」、親子ともに精神的に苦しくなることが多いのです。
ここで大切なのは、
「出席不足=怠け」ではないということ。
休みが増える背景には、実は次のような“理由”が隠れていることが多いです。
- 朝起きるのがつらい(睡眠リズムの乱れ)
- 人間関係の緊張・摩耗
- 授業についていけない不安
- 学校生活に“体力”が足りない状態
- 真面目だからこそ疲れてしまった
どれも「努力が足りない」ではなく、心が疲れているサインです。
まずは責める必要はありません。
では、いま何ができるか?
① 科目別に出席状況を確認する
担任や教務に「出席簿のコピー」や「ポイントの説明」をお願いして大丈夫です。
② 遅刻・早退のカウントを正確に知る
高校ごとに 遅刻3回=欠席1回扱い などルールが異なります。
ここが盲点になりやすいです。
③ 週単位で出席を管理する
「今日は行けた/行けない」ではなく、“今週どうだった?” の視点に変えると心が軽くなります。
④ 医療機関と連携する選択肢を知る
必要に応じて 「出席扱いの配慮」 を受けられるケースがあります。
高校は、「休みが続いたら終わり」ではなく、
支援・相談・調整のためのルートが用意されている場所です。
赤点・未提出物は“黄色信号”。救済ルートは必ず確認を

テストで赤点がついたり、提出物が期限に間に合っていない科目があるとき、
それは 「まだ間に合う黄色信号」 です。
ここで大切なのは、
「もうだめだ…」と止まってしまうことではなく、ここからどう動くか。
多くの高校では、赤点=即留年 ではありません。
実際には、
・補習
・追試(再テスト)
・追認指導(追加レポート・課題)
といった 救済ルート が、ほとんどの学校に用意されています。
つまり、赤点は「終わりの合図」ではなく、
「ここからが踏ん張りどころ」というサイン なのです。
では、高校の留年はいつ決まるのか?
最終的な判断は、2〜3月に行われる進級判定会議です。
しかし、赤点・未提出の“黄色信号”は、もっと前に点灯します。
具体的には、
- 2学期の期末テスト
- 冬休み前の成績仮決定
- 3学期開始時の状況確認
このあたりで、
「どの科目が危ないか」が明確になります。
ここを見逃さず、早めに動けたかどうかが、
その後の結果に直結します。
では、なぜ未提出物がこんなに大きな影響を持つのか?
高校の評価は 「テスト」だけではなく「平常点」も加わるからです。
平常点の例
- 小テスト
- ノート・ワーク提出
- 授業態度
- 課題の締切遵守
提出物が欠けると、平常点が下がる → 赤点に近づく → 救済が必要になる
という流れが一気に加速します。
そして、
「提出できない」の背景には、怠けではなく、整理の苦手さや不安の溜まりがあることが多いです。
だからこそ、
叱るのではなく、“一緒に整える” が効果的です。
今日からできる具体的な打ち手
① 科目ごとに「課題と提出状況」を棚卸し
紙でもアプリでもOK。
“現状が見えると、動ける力が戻る” ことは本当にあります。
② 追試・補習・提出締切の日程を担任に確認
先生は 「意外なほど助けようとしてくれます」。
③ 「1日で全部やる」ではなく「15〜20分×3回」に分ける
脳は「短時間の繰り返し」のほうが動きが戻りやすいです。
④ 提出までの道筋を細かく言語化する
例)「ワーク15ページ」→「今日は5ページだけ埋める」
これは やる気を出す方法ではなく、“動ける形にする方法” です。
そして、もうひとつ大事なこと。
赤点がある子は、劣っているわけではありません。
むしろ、
がんばりたい気持ちがあるのに、うまく回らなくなって苦しくなっている
そんな子がほとんどです。
今、不安を感じているあなたは、
お子さんを「見てあげている」人です。
だからこそ、まだ間に合います。
留年が確定した場合の選択肢は「原級留置」だけではない

高校で留年が確定したとき、多くの人が「同じ学年をもう一度繰り返す(=原級留置)」しか選べないと思い込みがちです。
ですが、実際には いくつかの進路や選択肢が存在します。
つまり、留年=人生が止まる ではありません。
むしろ、ここから 合う道を再構築するタイミングになる こともあります。
そしてまず確認したいのは、
高校の留年はいつ決まるのか?
最終的には、2〜3月の進級判定会議で決まります。
ただし、それは “選択肢を考えるスタート地点” でもあります。
① 原級留置(同じ学年をやり直す)
一般的な方法です。
同じ授業を再度受けることで、基礎の理解を取り戻せるメリットがあります。
ただし、友人関係が一度リセットされる負担が大きい場合もあり、
お子さんの性格や学校環境によって向き不向きが分かれます。
「同級生と違うことが不安」という悩みが出るケースでは、
学校側と“クラス配置”や“サポート教員”について相談する余地があります。
② 単位制・通信制高校への転入
留年が確定した際、転校して学びを継続する道もあります。
単位制高校・通信制高校は、
「いま持っている単位をそのまま活かせる」ことが多く、
一年分まるまるやり直す必要がないのが大きな利点です。
- 朝がつらい
- 人間関係で摩耗した
- 学校のスピードが合わない
そうした理由による不登校ぎみの子には、
環境を変えるだけで学習が再び回り始めることが珍しくありません。
最近は 通学型・週3型・オンライン併用型など、
選択肢がとても柔軟です。
「学校に行けなかった自分」ではなく、
「自分に合う学び方へ移る時間」として捉えられます。
③ 高卒認定 → 専門校・短大・大学へ進むルート
高校に戻る必要はなく、
「高卒資格同等の資格(高卒認定)」を取得して進路へ進む選択もあります。
特に、得意科目がある子・自分のやりたいことが明確な子にとっては、
「周りと同じペースで進むこと」を優先するより、
自分のリズムで学ぶ方が伸びやすいです。
留年=遅れるではなく、
「時間の使い方が変わる」だけです。
いま、親として大切な視点
「どれが正解か?」より、
「子どもが自分で納得して選べる状態か?」 が重要です。
そのために役立つ質問があります。
- 何が一番つらかった?
- どんなペースなら続けられそう?
- 誰と一緒にいたい?
この問いは、
“できない部分”ではなく、“本人の軸”に光を当てる質問です。
留年の判断は、
「過去の失敗を責める時間」ではなく、
これからどう生きるかを立て直す時間です。
そしてあなたがそばで見守っていることは、
すでに 何より強いサポート になっています。
高校 留年 いつわかる不安を減らす家庭サポート —— 英語を“得意”にして自信の土台を作る
家庭学習の重要性——小さな習慣の固定が“進級の保険”になる

高校での進級は、2〜3月の進級判定会議で最終的に決まります。
つまり、高校で留年がいつ決まるかというと「学年末」なのですが、実際にはその結果は日々の小さな積み重ねで左右されていきます。
ここで言う積み重ねとは、派手な努力ではなく、“家庭学習という小さな習慣”のことです。
家庭学習には大きく2つの意味があります。
ひとつは 学力を補うための勉強。
もうひとつは 「やるべきことをやれる力」を育てること。
この後者が、進級の保険になります。
留年につながりやすいのは、
「理解できないから」よりも、
“提出できない・積み残しが溜まる” というケースの方が圧倒的に多いのです。
実際、習慣と評価の関係を整理した記事として、
→ 「中学生の提出物遅れは成績に影響する可能性あり」
この中でも、小さな遅れが成績に強く響くことが解説されています。
高校でもまったく同じ構造です。
では、家庭学習がなぜ“保険”になるのか。
理由はシンプルで、
授業が少し難しくなっても、自力で立て直せる状態を保てるからです。
・ワークが溜まらない
・小テストで最低限の得点ラインを確保できる
・提出物を期限内に出すクセがつく
これらができると、
赤点や追試のリスクが目に見えて減ります。
逆に、家庭学習が定着していない場合、
ちょっとした体調不良・行事・人間関係の揺れで、
一気に 「追われる側」 になってしまいます。
ここで、現実的に取り組みやすい形を紹介します。
① 勉強時間を決めない
「何時からやる」ではなく、
「夕食前に15分だけ」 のように、場面で固定します。
② 教科を欲張らない
1日にやるのは 1科目だけ。
“広く薄く”は続きません。
“狭く短く” が習慣になります。
③ 親は「確認役」ではなく「伴走役」になる
やる気を出させる必要はありません。
「できたら見せて」だけで十分です。
高校生活は、完璧である必要はありません。
大事なのは、
止まらない形で続くこと。
そしてあなたが今、
「どう支えよう」と考えていること自体、
すでにお子さんにとって 大きな力 になっています。
進級は、
一気に決まるものではなく、ゆっくり積み上がるもの。
その積み上げは、
今日の 15分 から始められます。
まだ、間に合っています。
一緒に整えていきましょう。
高校の留年はいつわかる?まとめ

高校での留年がいつわかるかというと、
正式に決まるのは2〜3月の「進級判定会議」です。
ただし、結論だけを見ると「突然決まる」ように見えても、
実際の流れはもっとゆるやかで、その前からサインは積み重なっていきます。
- 出席不足は、その時点で進級が厳しくなることが多い
- 成績不振は「補習→追試→追認指導」で巻き返しが可能
- 単位認定は授業の“3分の2以上の出席”が基本
- 赤点・未提出物は“黄色信号”。救済ルートは必ず確認を
- 留年確定後も「原級留置」だけでなく、転校・通信制・高認と複数の選択肢がある
どれも、
「いま、どう動けるか」
「どこで立て直せるか」
が鍵になります。
そして何より、
家庭で支えるなら「小さな習慣」から。
家庭学習は“点数のため”だけでなく、
「自分を立て直す力」を育てるものです。
それが、**進級のための“保険”**になります。
もし今、あなたが
「不安だな…」
「間に合うのかな…」
と感じているなら、
それは “ちゃんとお子さんを見ている証拠” です。
あなたのそのまなざしは、すでに支えになっています。
焦る必要はありません。
止まらなくていい。
今日、できることを一緒に小さく整えるだけでいい。
高校生活は長いマラソンです。
つまづくことは、珍しいことではありません。
でも、そこからもう一度歩き始めた経験は、
その子の一生の「自力の土台」 になります。
あなたとお子さんは、まだ十分に間に合っています。
ここから、いっしょにやっていけます。

